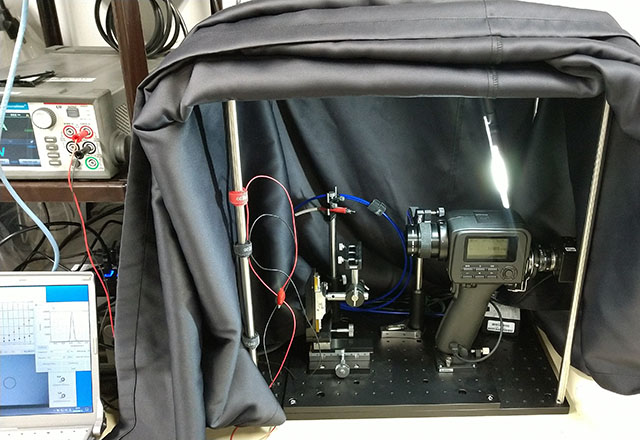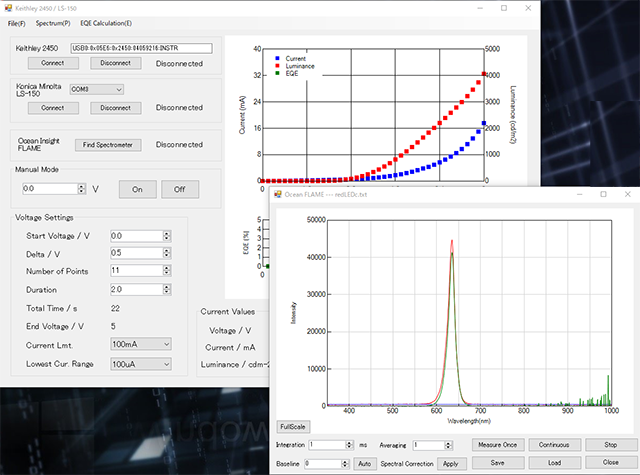あなたは
人目のご来訪者です

| ← 2020/10 → | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2020/10/21 (水) 量子ドットモニター もう何年も前に買ったPrincetonのモニターの1つに表示異常が頻発するので、ついに買い替えを決断しました。以前から量子ドットモニタ―に興味があり(笑)っていうか欲しくて仕方がなかったのですが、Samsungや数少ない日本メーカーのだと中級機種以上のラインアップで27インチ以上が主流。Full HDを横に2台置きする前提なので、机や視線移動の関係から24型が限界なのです。24型の量子ドットモニターは長らく存在しなかったのですが、1年ほど前に恵安が出してきました。と言っても中国のどっかから持ってきたものです。2万円切ってたし、これを2台買いました。 |
|
2020/10/19 (月) 対面授業半数以下の大学名公表 とかする前に、 |
|
2020/10/17 (土) セカンドSIM OCNモバイルに変えたら機種代の割賦含めて月々1万円以上払っていた携帯代が2千円になって、ついでにAmazon Musicカウントフリーで大変嬉しい最中なのですが、折角なのでMVNOのメリットをもう一つ享受したいという思いがありまして、それがセカンドSIMカードなのです。 |
|
2020/10/12 (月) なんとかPay 気が付いたらPayPayにチャージできなくなって、もうすぐ一カ月。まさかそんな大きい事件になるとは思わなかったです。たまにアプリを起動すると「セブンイレブンで現金チャージできます!」の通知が何通も入ってるのですが、そこまでしてPayPay使うかっていう話。 |
|
2020/09/27 (日) Uray Encoder コロナ禍で対策丸投げの文科省に代わって各大学(小中高もかな)で工夫が進められています。その煽りというか、末端仕事を引き受けることになりました。 |
|
2020/09/22 (火) プログラミング教育 小中高でプログラミング教育が始まっているように、言語の問題を除いては国民の必須スキルになりつつあるのですが、SEにでもならない限り将来にわたって書き続ける人はごく僅かでしょう。私はそんな世代ではないので、大学以降に趣味として始め、独学でリファレンスを見ながらVB.NETやExcel/Access VBAを何とか書けるレベルですが、でも時々役に立ちます。 |
|
2020/09/21 (月) ぎっちょ この業界にいると結構左利きが多いことに驚かされます。かくいう私も矯正された「箸」と「鉛筆(ペン)」そしてなぜか「マウス」以外は今でも左利き。スポーツはまじめにやってないのでイマイチわかりませんが、まあどっちでやっても同じくらいヘタクソです。ただ、幼少期には存在しなかった動作(自動改札にICカードをタッチする、スマホを触る)あるいは環境的にやらなかった動作(スパチュラでフラスコに粉を入れる、ピペットを操作する、化学合成の操作をする、電顕ホルダーの先端にサンプルをセットする)などは左右問わず体と対象物の位置次第で都合の良い方を選びます。今は矯正はよくないって風になってるんでしょうか。そしてペンに取って代わったキーボードは両手作業です。 |
|
2020/09/20 (日) PayPay 7年前からFelica式のおサイフケータイで複数のブランドをスマホに入れ、便利に使ってきたんですが、キャッシュレス決済還元の一時できなブームでQRコード決済を導入する店が増え、挙句の果てには(店舗手数料の面で不利だった)Felica式のEdyやWAONを辞める店が出てきたので、半年ほど前からPayPayも入れて使っていました。キャッシュレス還元が終わってからは、ひと手間必要なPayPayからおサイフケータイに戻った感がありましたが、それでも千円以下の飲食店からホームセンター、薬局、電器店で使え、数千円〜数万円の買い物でも現金不要、カード払いのサイン不要っていう「隙間」を埋める存在として便利なサービスです。何と言ってもパスワードなしで10万とかチャージできるのが、上限5万だったいするおサイフケータイには無い利点。でもハード的にガチガチに本人確認しているおサイフ〜でも上限がキツいのに、こんなユルユルで大丈夫かな?という心配は少しばかりありました。 |
| a-Nikki 1.06 |
| Last Update: 2020/11/04 01:04:17 |